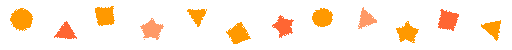
感想文集=会員の皆さんの感想文です
お父さんはふっくらした体格でリズムカルに動き、芝居もよい味を出していた。 長男 印象に残った。ギターを弾く男の人がおどけて面白かった。女の人もよく通る声で聴きやすかった。 みんなお芝居が揃っていた。やっぱり本職は違うなあと思った。 石蕗 傘寿の母 |
| ロシアの喜劇の作品は初めて観た。お国柄が違っても喜劇の精神は同じなのだと実感する。 家族が崩壊しようとしているところに二人の青年が現れることから物語はどんどん展開されていく。 嘘と分かっていても、次から次へと思いつきを語るうちに、父・サラファーノフは自分の過去の若き思いでのなかにもしや自分子どもいたのだと確信させるフスイギンの演技には思わず喝采するのでした。 二人の青年の掛け合いはまさに喜劇そのものでした。引いたり進んだり、行きつ戻りつの演技は面白かった。 最後に父親の音楽に関わる真実が分かるのだが、それを問題とせず家族の絆が再び甦っていく。 物語は深刻なのに喜劇で演じることで楽しめる舞台でした。 ねむの木 T・O |
「こいつは、あなたの息子なんです。」と言われて、私たちのうちの誰がその言葉を信じることが出来るだろうか?しかも、初対面の相手から。 しかしアンドレイ・サラファーノフは、すっかり信じ込んでしまう。なんと、彼には“心当たり”があったのだ!そしてドタバタのなかで、彼の息子も娘も “新しい家族”を、 “長男 ”として受け入れていく。そして、嘘を打ち明けたあとも、長男への愛と信頼は壊れない。 むしろ、トラブルメーカーの彼を通して、サラファーノフ家の “家族の絆”は再生する。 客席から見ていて、「そんなアホな!」と突っ込むと同時に、「なんか、ええなぁ」とホッとした。 劇中の言葉に「人は心に鎧をまとっている」とあった。 現在の世界を見渡すと、「確かにそうだ!」と思わせるほど、独善的で疑い深い出来事のなんと多いことか。 だからこそ、「こんな人、こんな家族がいたら」「うちの家族もこんなふうに信じあい、愛し合いたい。」という想いを抱くのだろう。私も、まるで藤山寛美の松竹新喜劇で人情噺を観たあとのように、しみじみほっこりした。 「洋の東西を問わず、人間はやっぱり “情 ”や “絆 ”があってこそ。」と感じさせてくれた。 もし、こんなにも幸せな気分にさせてくれる出来事が待っているなら、何かに乗り遅れるのも悪くないなと思う。 ゆうやけこやけ H・K |
| 演劇という人間のドラマには、「気付き」がある。 興奮や感動の後に、「気付き」という余韻がある。 人は一人では生きてゆけないから、人を知ろうとする。「人の心とは」を理解するためにはまず自分を知らなければならない。「人の心」=「感情」は経験でしか理解できないという訳だ。それも生活するだけの単純な人生で得られる経験では限界があるのだ。今は書物や映像からその何倍もの経験が補てんできるすばらしい時代になった。 演劇もその経験ができるツールのひとつで、その効率からいえば一番かもしれない。 理解ができれば、これからどう生き、どう振舞えば、よりすばらしい人生を送ることができるか解って来るのだろう。 もし、あんな立場に立ったら、私はどうしただろう。こんな人にだけはなりたくない。逆に、こんな人になりたい。 「気付き」の数が多ければ多いほど、幸せになれそうな気がする。 このお芝居でそんなことを思った。 誠実に生きようと思った。 自分を客観的に見て生きようと思った。 人にやさしく生きようと思った。 嘘をつかれても許そうと思った。 子供に依存しないように生きようと思った。 今の幸せを思った。 演劇のある人生は、すばらしいと思った。 今治という町はすばらしいと、あらためて思った。 演劇を多くの人に見せてあげたいと思った。 市民劇場を失くしてはいけないと思った。 エメラルド A |
| バックナンバー | 「砦」の感想文 |
トップページへもどる