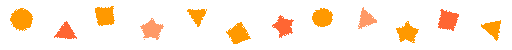
最新例会紹介
2003年 11月24日(月) 場所:今治市公会堂 開演6:30 開場6:00 東京ヴォードヴィルショー 三谷幸喜の傑作コメディー 『その場しのぎの男たち』 出演 佐藤B作・佐渡稔・石井愃一・市川勇・あめくみちこ 瀬戸陽一郎 山本龍二 他 作 三谷幸喜 演出 山田和也 ★ とにかく、わらってください。 ★ 明治という時代を背景に、世界の海に日本という 小舟を漕ぎ出した男たちの滑稽にして懸命な チャレンジ・ストーリーの顛末…。 |
| あらすじ |
| 明治24年の5月11日朝、大津市の路上で来日中のロシア皇太子ニコライが巡査・津田三蔵に襲われる。世にいう「大津事件」である。 わずか組閣5日目の松方正義内閣にとって日本の命運にかかわるこの大ピンチは汚名返上の千載一遇でもあった。 内相・西郷従道、外相・青木周蔵、逓信大臣・後藤象二郎と共に無い知恵を絞って編み出す「その場しのぎの対応策」は、 打つ手打つ手が面白い様に外れていき、そこに農商務大臣・陸奥宗光、伊藤博文とその右腕・伊東巳代治が加わり、ますます混乱の深みにはまっていく。 かたや冷徹なまでに日本の政治に命をかける伊藤博文と、かたや気のいいばかりでどうしても一流になりきれない 三流政治家松方正義とその仲間達の生き方の違い…。 |
| 《大津事件の解説》 ◎一大凶事の発生 明治24年5月11日、来日中の帝政ロシア皇太子ニコライが滋賀県大津市の路上で切りつけられるという凶事が起こった。 現場で叔り押さえられた暴漢は、こともあろうに琵琶湖観光中の皇太子警護にあたっていた巡査津田三蔵と判明。犯行の動機は、 ニコライが日本侵略のため状況視察の密命をおびて来日したと考えたためといわれる。報復のためにロシアが攻めてくるかもしれない。 開国後の混乱を次第に整備し、ようやく本格的に近代国家への道を歩み始めた日本は大国ロシアを相手に一大危機に直面する。 こうして時の松方内閣はじめ政府高官はもちろん、日本という国にとって 「明治の一番長い日」が始まったのである。 ◎遭難した皇太子ニコライ ロシア帝国皇太子ニコライ・アレクサンドロビッチは、明治政府が列強から招いた最初の国賓であった。 明治24年4月27日、ロシア軍艦七隻とともに長崎に人港したニコライは皇族・政府高官による出迎えを受け、盛大な歓迎行事が催された。 皇太子を一日見ようと市民も黒山の人だかり。辻々には日の丸の国旗が掲げられ、幕が張り巡らされ、国をあげての大歓迎であった。 ニコライはその後、 長崎から鹿児島に島津氏を訪ねた後、神戸に向かい、5月9日京都・常盤ホテル(現在の京都ホテル)に到着した。 京都では異例の時期に大文字焼きに灯がともり、 皇太子を歓迎した。東京での明治天皇との会見を前にして三日間の京都滞在。 その最終日、琵琶湖観光に大津に赴いたニコライは帰途についた 人力車上で災禍に見舞われたのである。 ◎事件の経過 5月11日午後1時30分頃。京都に帰るニコライを乗せた人力車は警備の警官と見送りの市民が沿道を埋める中を走っていた。と、 突然一人の警官が腰に下げたサーベルを引き抜くや、車上のニコティに切りかかったのである。打撃は2回。いづれも頭に当たり、 ニコライはあわてて車から飛び降り逃げだした。突然のことに呆然とする市民と他の警官たち。追いかける氾人を取り押さえ、 皇太子の急を救ったのは車を引いていた二人の車夫であった。ニコライの傷は右側頭部に二カ所、付近の呉服屋の店先で応急手当を受けた後、 京都ホテルに戻り縫合手術を受けた。現場で取り押さえられた皇太子襲撃犯人は、滋賀県守山署の巡査・津田三蔵(37歳) であった。 ◎凶報走る 明治政府の動揺露国皇太子、警護の警官に襲撃さる!事件後の午後2時30分頃、政府に届いた第一報は政府にとってあまりにも衝撃的であった。 午後4時、明治天皇を交えた御前会議が召集される。ロシアの反応はいかに、報復か、賠償か、金か、領土の要求か、 予測のつかないロシアの態度と乱れ飛ぶ情報に会議は混迷した。 ◎政府要人、続々と京都入り おりしも、当時の松方正義内間は発足から5日目を迎えたばかりであった。 そこにこの重大事件の勃発で思わぬ困難な局面に立たされることとなったのである。政府全体が京都に引っ越してきた如くといわれたように、 事件直後から次々と京都に乗り込んできた高官たち。首相松方、閣外にありながら隠然たる権力を握っていた伊藤博文はじめ政府首脳陣は、 協議を重ね事態収拾に頭を痛めることとなる。 ◎明治二四年という年 維新開国後、諸外国を規範としつつ近代国家への改革を遂行してきた日本であったが、 真に近代国家としての体制が整い、機能し始めるのは20年代に入ってからである。その中で、24年は明治政府のひとつの転換期にあたる。 すなわち、12年の内閣制度発足、22年の憲法発布(23年施行)、23年の国会開設と政治制度はようやく体裁を整え始める。 また、外交的にも、維新以来懸案となっていた諸外国との不平等条約改正に向けて展開された極端な西欧迎合的な「鹿鳴舘外交」が事実上失敗に終わり、 新たなる対外政策が重要課題として求められていたのもこの頃である。アジア情勢や国際情勢へ日本が大きく関わっていくその後の歴史の前夜、 それが明治24年当時の状況であった。一方、当時のロシア帝国は 「世界の六分の一を領有している」 といわれたほどの勢力を誇っていた。 西はバルト海沿岸でヨーロッパ諸国と接し、南は黒海付近で紛争を繰り返しつつ南下政策を押し進め、またウラジオストックに拠点をおいて東ににらみを利かせていた。 明治8年の千島・樺太交換条約をはじめとしてロシアの極東進出は日本にとってかねてより神経のとがる問題であった。 そしてその不安を決定的にしたのが、まさにこの年(1291年) に発表されたシベリア鉄道建設計画である。 他ならぬ皇太子ニコライ自身が、訪日後の6月にウラジオストックで開かれるシベリア鉄道起工式に出席することになっていたのである。 そんなおりもおり、大国ロシアとの政治危機を招きかねない重大事件が勃発したのである。 |
ひとつ前の例会は?
| ☆☆ 今後のラインナップ ☆☆ |
トップページへもどる |